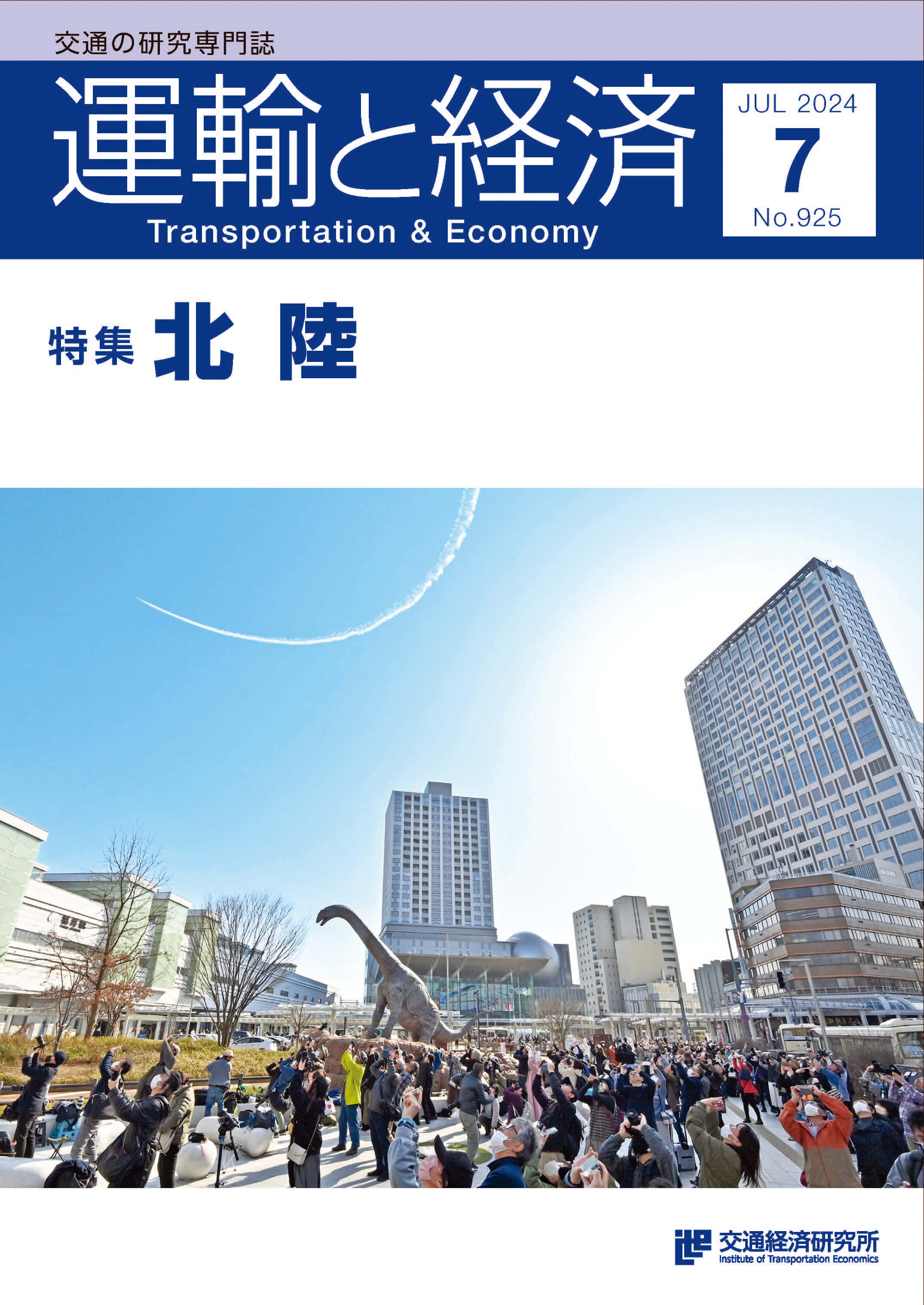< 年別リストへ戻る
在庫:
なし
| 特集 | ||
| 巻頭言 | ||
| ● | 北陸と交通 | |
| 羽藤 英二 (東京大学大学院工学系研究科教授) | ||
| 座談会 | ||
| ● | 新幹線開業を機に変貌を遂げる北陸の未来 | |
|
漆原 健
(西日本旅客鉄道株式会社取締役兼常務執行役員 前 常務理事金沢支社長) |
||
| 小中出 佳津良 (加賀商工会議所副会頭・小中出建設株式会社社長) | ||
| 中村 保博 (福井県副知事) | ||
| 羽藤 英二 (東京大学大学院工学系研究科教授) | ||
| 論稿 | ||
| ● | 新しい取り組みを発信し続ける北陸の地域鉄道 | |
| 中川 大 (京都大学名誉教授・富山大学特別研究教授) | ||
| ● | 北陸新幹線敦賀開業が地域経済に与える経済効果 | |
| 松原 宏 (福井県立大学地域経済研究所長・教授) | ||
| ● | ハピラインふくいの発足と利用促進の取り組み | |
| 株式会社ハピラインふくい | ||
| ● | 北陸、越前地方の官設・幹線鉄道 | |
| 小谷 正典 (福井県立大学経済学部特任講師・地域経済研究所客員研究員) | ||
| インタビュー | ||
| ● | 新幹線開業後の福井県の移住・定住促進施策 | |
| 三津谷 勇気 (福井県交流文化部定住交流課移住定住グループ主任) | ||
| 論稿 | ||
| ● | 北陸の経済産業動向と能登半島地震からの復旧・復興 | |
| 根本 博 (金沢学院大学経済学部特任教授・北國総合研究所研究員) | ||
| ● | 令和6年能登半島地震からの復旧・復興を支えるTEC-FORCEの活動について | |
|
菊地 弘之
(秋田県建設部次長 前 国土交通省大臣官房参事官(運輸安全防災)付安全防災対策官) |
||
| ● | 明治期の能登半島の海運と産業化 | |
| 中西 聡 (慶應義塾大学経済学部教授) | ||
| ● | ネットワークに見る蓄積の力とクビキ:道と水に視点をおいて | |
| ~能登半島地震をどう読み解くか?~ | ||
| 家田 仁 (政策研究大学院大学特別教授・東京大学名誉教授) | ||
| 連載 | ||
| 交通のいま | ||
| ● | 海の金沢とレール&クルーズ | |
| 久保 光夫 (石川県商工労働部港湾活用推進室室長) | ||
| ワンポイント解説 | ||
| ● | 地域における文化観光の推進に向けて | |
| 三木 直樹 (文化庁参事官(文化拠点担当)付 参事官補佐) | ||
| 竹内 寛文 (文化庁参事官(文化拠点担当)付 文化観光支援調査官) | ||
| 鉄道がつくった街・人・文化 | ||
| ● | 昔の駅弁、今の駅弁 | |
| 岩成 政和 (鉄道研究家) | ||
| 交通時評 | ||
| ● | ライドシェアと総合的交通政策 | |
| 市川 嘉一 (都市・交通ジャーナリスト) | ||
| 海外交通探訪 | ||
| ● | ベトナムにおけるホーチミン市都市鉄道1号線: | |
| 開業への困難な道のり | ||
| HO SY QUOC (一般財団法人運輸総合研究所研究員) | ||
| 研究室紹介 | ||
| ● | 地方の公共交通政策推進に向けた教育・研究活動 | |
| 榊原 弘之 (山口大学大学院創成科学研究科教授) | ||
| 鈴木 春菜 (山口大学大学院創成科学研究科准教授) | ||
| 交通経済研究所 | ||
| 交通トピックス | ||
| ● | ドイツ鉄道によるダイナミックプライシング | |
| 土方 まりこ (交通経済研究所主任研究員) | ||
| 資料室便り | ||
| ● | 資料室便り | |
| 資料室 | ||
| 日本交通学会 | ||
| 活動報告 | ||
| ● | [関西部会5月例会 報告概要①]鉄道会社が主催するウォーキングイベントの価値評価 | |
| ―トラベルコスト法を用いた社会的余剰分析― | ||
| 藤井 成弥 (広島商船高等専門学校 流通情報工学科 助教) | ||
| 水谷 淳 (神戸大学大学院海事科学研究科 准教授) | ||
| ● | [関西部会5月例会 報告概要②]航空貨物輸送関係イベントの影響に関する予備的分析 | |
| ―イベントスタディを用いた考察― | ||
| 朝日 亮太 (九州産業大学商学部准教授) | ||
| 編集後記 | ||
| ● | 編集室から | |
| 赤池 弘友紀 (交通経済研究所専務理事) | ||
| 亀山 紘樹 (交通経済研究所研究員) | ||